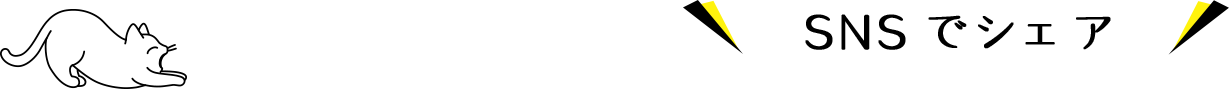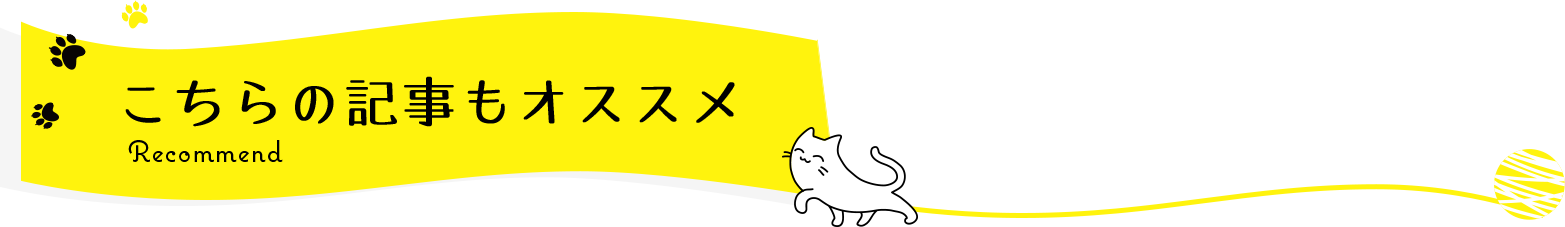「狂犬病」と聞くと、犬がかかる病気で猫には関係ないと思っていませんか。しかも「狂犬病」という病気自体が、もう過去の病気だと思っていませんか。
しかしこれはどちらも違います。猫も狂犬病にかかることがありますし、海外では現在も数多くの発生報告がある病気です。発症するとほぼ必ず死亡するとされる狂犬病、猫もこの恐ろしい病気と決して無関係ではないことを忘れないでください。
狂犬病は発症するとほぼ100%死亡する
狂犬病とは「狂犬病ウイルス」の感染により発症してしまう感染症です。「狂犬病」という名前ですが、犬だけでなく全ての哺乳類が感染し、発症してしまう可能性のある病気になります。
ですから猫が感染してしまうこともありますし、もちろん人だって感染の危険性があります。他にコウモリ・アライグマ・スカンク・キツネ・ウシ・ウマなど、いろいろな哺乳類で発生が報告されています。
現在の日本では、狂犬病が話題になることはほとんどありません。日本で最後に狂犬病の報告があったのは1957年で、実はこのときは犬ではなく広島県の猫でした。それ以来50年以上も、日本では狂犬病の発生報告は出ていません。
半世紀以上前の日本では、狂犬病がかなり流行していた
日本では半世紀以上発生報告のない狂犬病ですが、その少し前までは危険な感染症として恐れられていました。ほんの50年ちょっと前の日本では、狂犬病の大流行が何度か起きているのです。
この頃、たくさんの犬が狂犬病を発症して死亡していました。犬だけでなく牛や馬などの家畜動物にも感染し、大きな問題になっていました。そして感染は人にも広がっていて、狂犬病で亡くなってしまうという人も多くいたのです。
そのようなことがあり、1950年に制定されたのが「狂犬病予防法」です。この法律によって飼い犬には登録とワクチン接種が義務化されました。同時に野犬の駆除なども行われ、それらのおかげで1957年の発生を最後に、その後は狂犬病発生の報告はありません。
わずか7年で、狂犬病を撲滅することができたのです。現在、日本は狂犬病の清浄国(狂犬病が撲滅された国)とされています。
世界では今も狂犬病が多く発生している
しかし世界では、今なお狂犬病は脅威の感染症とされています。毎年、多くの狂犬病が発生し、感染して亡くなってしまう人もたくさんいます。
全世界での狂犬病の死亡者数は、毎年約55000人とされます。その中でも実はアジアでの発生数はかなり多く、特にインドや中国ではたくさんの人が亡くなってしまっています。
狂犬病の清浄国は日本・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・スカンジナビア半島の国々など、数カ国のみとされます。狂犬病は、世界中の多くの国で(しかも日本のすぐそばの国でも)今も多く発生している感染症なのです。
先ほど、日本では50年以上発生していないと言いました。しかし海外を旅行中に感染し、日本へ帰国した後に発病して死亡してしまった事例は数件あります。日本人観光客がよく訪れる人気の観光地でも、狂犬病は多く発生しているため気をつけなくてはいけません。
▼タイや台湾は猫がたくさんいる親猫国ではありますが、残念ながら狂犬病はまだ根付いているんです
タイは猫だらけ!タイのいろんな地域で出会ったかわいい猫たち
台湾の猫村、ホウトン旅行記。世界6大猫スポットは町中猫だらけ!
さらに世界のグローバル化により、日本に狂犬病ウイルスが侵入してきてしまうリスクがないとは言えません。万が一の対策は必要なのです。
狂犬病の動物に咬まれると猫も感染する危険が!
狂犬病にかかった動物の唾液の中には、狂犬病ウイルスがたくさん含まれています。そして狂犬病にかかった動物に咬まれると唾液に含まれるウイルスが侵入し、それにより感染することになります。
アジアでは犬が主な感染源になっていますが、猫が感染源になることもあります。人から人へと感染することは、通常はないとされます。
ウイルスは体内に侵入すると、神経系に感染します。1日数センチの速さで神経を伝わって増殖していき、少しずつ中枢神経系へと向かっていきます。そしてやがて中枢神経系に到達すると、とうとう狂犬病を発症してしまうのです。
咬まれた場所によって潜伏期間は違ってきます。頭の近くを咬まれた方がウイルスが中枢に到達するまでの期間が短くなり、そのために狂犬病を発症するまでの期間も短くなります。足を咬まれた場合には、発症までの期間がもう少し長くなります。
とは言え、猫は体が小さいためウイルスが中枢に到達してしまうのも早くなります。犬の場合の潜伏期間は2週間~2ヶ月程度とされますが、猫はそれより短く2~3週間とされます。
そしてもしも狂犬病を発症してしまうと、その猫は100%死亡してしまうことになります。猫だけでなく、狂犬病を発症した動物は全て必ず死亡するとされます。
ちなみに発症する前に、狂犬病ウイルスに感染しているかどうかを検査する方法はありません。そして狂犬病を発症してしまうと、残念ながら治療する方法は何もありません。もうそこには、死しかないのです。
人の場合には、咬まれた直後にワクチンを連続して接種することで生存できる可能性があるとされています。またワクチンなしでも発症後に回復できた例が数件ありますが、治療法として確立されているわけではありません。多くの場合は、発症するとほぼ100%死亡します。
狂犬病の症状はあっという間に進行する
狂犬病ウイルスに感染すると、2~3週間の潜伏期間(最長は51日の記録あり)を経て狂犬病を発症してしまいます。
狂犬病は「狂躁型(きょうそうがた)」と「麻痺型(まひがた)/沈鬱型(ちんうつがた)」に分類されます。猫の場合には90%が狂躁型になるとされます。ちなみに犬の場合には、狂躁型は75%ほどと言われています。
「麻痺型/沈鬱型」では凶暴になることはありません。喉やあごの筋肉が麻痺して食べることができなくなり、水も飲むことができなくなります。その結果衰弱していき、全身が麻痺し昏睡に陥って死亡します。
いずれの型の場合にも、前駆期・狂躁期・麻痺期を経て死亡します。その経過はあっという間で、死亡するまでは1週間以内とされます。ほとんどは2~6日程度でしょう。
狂犬病の経過についてみていきましょう。
前駆期(1日)
狂犬病を発症した直後には、猫は今までとは性格ががらっと変わったようになります。いつもとは違う、異常とも言える行動をとります。
例えば普段はあまり甘えてくれない猫がやたらと甘えるようになり、すり寄ってきて愛情表現をしてくれます。逆に今まで懐いていた猫は、急に噛み付いたりするようになります。また物陰に隠れるようになったりということもあります。
狂躁期(2-4日)
狂犬病を発症して2-4日ごろは狂躁期とされます。この時期は非常に攻撃的になり、人や他の動物を襲うようになります。じっとしていることがなくなり、常に鳴き続けます。全く眠らなくなり、ヨダレをたくさん垂らすようにもなります。
発熱で口唇や舌などが紅潮したり、瞳孔が拡大したりすることもあります。「攻撃」「紅潮」「ヨダレ」「瞳孔拡大」が猫の狂犬病の4大徴候ともされています。
▼近年新たに発見された猫の病気・激怒症候群も突然攻撃してくるようになるという特徴があります
猫の新しい病気、激怒症候群(突発性攻撃行動)。症状、原因は?
麻痺期(3-4日)
狂犬病を発症して3-4日すると、喉の筋肉は麻痺してものを飲み込むことができなくなります。それによりヨダレはさらにひどくなり、ご飯を食べたり水を飲んだりすることもできなくなります。
その後麻痺は全身に広がり、呼吸ができなくなり意識も低下して死んでしまいます。
麻痺型の狂犬病では狂躁期がはっきりとはせず、前駆期から麻痺期になることもあるとされます。
なお、狂犬病の猫のヨダレには狂犬病ウイルスがたくさん含まれているため注意しなくてはいけません。狂犬症する3-4日前くらいから、ヨダレにはウイルスが含まれているとされます。
猫にも狂犬病予防のワクチンはある
犬の場合、狂犬病予防法によって狂犬病ワクチンの接種が義務付けられています。猫の場合にはワクチン接種の義務はありませんが、ワクチン自体は猫用のものが存在しています。
ただ日本国内で、完全室内飼いをしている猫の場合には接種の必要はないと考えられています。もしも猫を連れて海外へ行く場合には、接種することを検討しても良いかもしれません。
接種を希望する場合には、まず動物病院へ連絡をしてから受診するほうが良いでしょう。直接動物病院を受診しても、すぐに猫用のワクチンが用意できないこともあると思われます。
▼動物病院に電話で問い合わせをする場合には、24時間対応の電話サービスを活用しましょう
動物病院に電話相談だけってできる?メリットや費用について
海外旅行するときには、狂犬病への注意も怠らないで
日本国内にいると、狂犬病について不安になることはほぼないでしょう。しかし地球全体を見ると、まだまだ狂犬病は撲滅できておらず非常に危険な感染病です。海外旅行をされるときには、そのことを忘れないでください。
旅行先によっては、人間用の狂犬病ワクチンを受けて行った方が良いでしょう。また猫を連れての旅行の場合には、猫もワクチン接種しておいた方が良いかもしれません。
狂犬病の感染源となる動物は、アジアでは95%が犬とされます。それに比べて猫が原因で人に感染してしまう可能性は高くありませんが、猫からの感染報告もあります。
猫が感染してしまった場合には容易に室内に入り込みますし、犬よりも機敏な動きをするために噛み付かれたり引っかかれたりしやすくなります。ですから注意しなくてはいけません。
また海外で猫に出会ったときはついつい触れ合いたくなりますが、その猫が狂犬病に感染しているかもしれないということを忘れないでください。できれば海外では、不用意に動物に触れないほうがよいかもしれません。