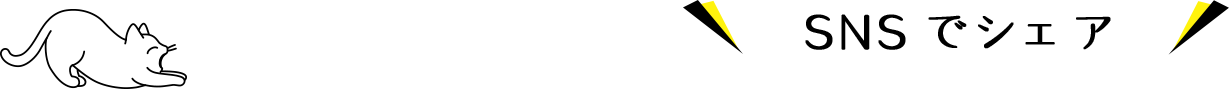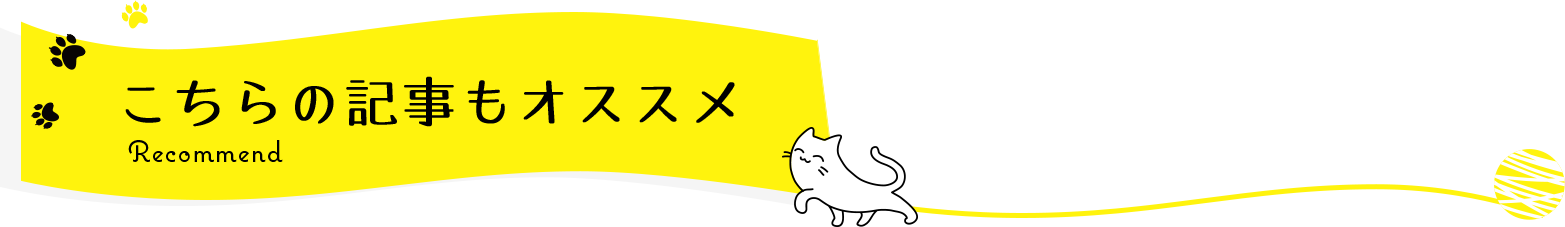猫は現在、人間の住む所なら世界中どこにでも居て、私たちの暮らしの中で非常に身近な存在と言えます。
飼い猫の起源はエジプト、そして古代エジプトでは神とも崇められ大切にされていたというエピソードは猫好きなら誰もが知るところでしょう。
それでは他の国、他の宗教ではどんな風に扱われる存在だったのでしょうか。ところ変われば猫変わる、宗教の中の猫の立ち位置についてご紹介していきます。
猫と人の出会いはエジプトから
人間が猫と暮らしていた痕跡は、実はエジプトより古い時代のものが各地で発掘されています。しかし発見される痕跡の少なさから、ヤマネコを代々家畜化することは容易ではなかったと考えられています。
そのため、各地で馴致が進められていったのではなく、エジプトが飼い馴らしたリビアヤマネコが世界各地に広がり、現代のイエネコのルーツとなりました。
太陽神ラーを崇拝する古代エジプトでは太陽フレアに似たたてがみや、夜にも目を光らせて活動する事からライオンを神聖視していました。ミニマムなライオンともいえる猫はまさに神の化身にうってつけの存在です。
猫の獰猛な一面はラーの娘でライオンの頭部を持つ女神セクメトとして、猫の愛らしさやネズミやヘビから人々を守る面は猫の頭部を持つ女神バステトとして崇拝されました。
大切な神の化身であり、生活のパートナーでもある猫、エジプトは当然国外への持ち出しを固く禁じていましたが、交易していたフェニキアの商人たちが少しずつ持ち去ってしまいます。珍しい家畜の密輸が目的でもありましたが、航海中に船のネズミを捕らせたいという実利的な理由もあったようです。
こうした交易船を通じて猫はギリシャからローマ帝国、ペルシャからインド、そして極東方面へと広まっていく事となります。
まだ未発達の文明社会において、人が生き延びるには様々な苦労が伴います。人知のみでは乗り越えられない艱難辛苦を支えるために、また共同体の維持のために、宗教は現代よりずっと大きなウェイトを占めていました。
世界中に広がっていった新しい動物”イエネコ”たちはその土地ごとの宗教によって運命を翻弄されることとなります。
古代宗教における猫①ペルシャとローマ帝国~ヨーロッパ
まずはペルシャに渡った猫たちから。古代ペルシャは善神アフラ・マズダを崇拝するゾロアスター教の国でした。
人間に忠実な犬はこの善神に与する存在として1/3ぐらいは人間同然とまで称えられていましたが、そうした思想のもとでは猫の自由気儘な性質は良しとされず、悪神アンラ・マンユの生み出したものとして忌み嫌われてしまいます。
蛇を忌むので、猫が蛇のように丸くなって眠る姿や蛇に似たシャーッという威嚇音も同様に嫌われてしまいました。
ところがギリシャ経由で猫が渡ったローマ帝国では初期の港町ベレニケからペット専用墓地が出土しており、埋葬された猫が多く見つかっています。
キリスト教以前のローマ帝国はミトラ教であり、これはエジプト同様に太陽神を頂点に置く多神教であったため、一神教であるゾロアスター教と違って猫を忌む戒律も無く、猫はペットとして可愛がられていたようです。
古代ローマとかかわりの深かったケルト人たちも太陽神ルーを主神とした多神教徒であり、猫を神聖視していました。その神話の中ではケット・シーと呼ばれる二足歩行する猫の妖精や、猫たちが人間とは違う世界の王政社会に属しているとされる伝承が残されています。
更に北上して北ヨーロッパで信じられてきた北欧神話では、愛と豊穣を司る女神フレイアの乗る戦車はベイグル(蜂蜜)、トリエグル(琥珀)という巨大な猫が牽引するとされていました。
この2匹はよく人気の大型猫ノルウェージャンフォレストキャットになぞらえられますが、猫がエジプトを発って北ヨーロッパに至るより以前から言い伝えられてきたので、イエネコではなくヤマネコだと考えるのが自然でしょう。
こうして猫たちは新しい土地でも大方すんなりと土地の宗教に溶け込み、古代の多神教においては神聖視されていきます。しかしそれが後世キリスト教の隆盛期、猫の受難に繋がっていくのです。
キリスト教における猫
キリスト教の前身、ユダヤ教ではたくさんの厳しい戒律を旨としますが、その中では動物に関する制約も多く「足にかぎづめのある生き物」もまた禁忌とされていますので、決して猫に好意的な世界ではなかったことが窺い知れます。
そういった素地のためか、はたまたエジプトを敵視して意図的に排除したためか、
聖書の中には猫が登場していません(外典に一ヶ所だけ、偶像崇拝を批判する例の中で登場します)。
聖書ではない伝承レベルではキリストが誕生するとき同じ馬小屋で猫もお産をしていて、生まれた子猫は十字架の模様(トラ模様でしょうか?)を持つことになった、ノアの方舟に載せたライオンがくしゃみをして生まれたのが猫である等々…猫とキリスト教にまつわる逸話が多く残されています。
神が作りたもうた人間のみが世界の万物の頂点であり、動物は魂を持たないとされるなど、もともと動物全般に冷淡なキリスト教ですが、13世紀トマス・アクィナスが神学大全に「人間以外の動物は大切にしなくても良い」と明記した事で猫を大切にしなくても宗教上問題ないという認識が確立されます。
とはいえ魔女狩りが本格化する以前に描かれた宗教画には”最後の晩餐”の片隅や”受胎告知”の足元に猫が描かれている事も多く、民衆に聖書の出来事を身近に感じさせるのに一役買っていました。
そして16世紀ごろから悪魔崇拝と猫がイメージとして結び付けられ、のちの魔女裁判へと繋がっていきます。
勢力拡大を図る為政者や聖職者にとって、キリスト教こそが唯一正しい宗教であると示すためには異教を否定し、異教徒を排除しする必要がありました。古代宗教で神格化されていた猫を貶めるのはイメージ戦略としてうってつけだったのです。
猫を飼っているだけで魔女とみなされ迫害される数世紀を経て、18世紀ごろからようやく道徳心によって動物も大切にするべきではないかという気運が高まり、19世紀ごろ猫はようやく愛すべきペットの座に復権します。
ギリシア正教の聖地、アトス山は今も女人禁制で家畜に至るまで徹底して雄ばかりですが、猫に限っては雌雄が許されて増える事が望まれています。
ロシア正教会の司祭有志が近年発行して賛否両論の物議を醸した「司祭と猫」のカレンダーシリーズに対し、正教会の広報責任者は全肯定しないまでも「大体の司祭は猫を飼っているし、教会には猫がいる」とコメントしています。
宗教上の立ち位置は低くとも、実際のところは末端の修道院では貴重な羊皮紙や食料をネズミから守るために猫は重宝されていたのでしょう。
イスラム教における猫
万物に神性を見出す多神教に対し、一神教は厳格な教義や戒律を持つことが多く、前述した一神教ではすべて気儘に行動する猫に対して好意的ではありません。その点で異色なのがイスラム教です。
猫は礼拝所へ自由に出入りが許され、なんなら礼拝前に使うための清めの水に口を付けても水が穢れたとはみなされません。人間用の食器からごはんを食べる事も認められていますし、むしろ猫にごはんをあげる事は天国が近づく善行とみなされます。
食中毒を招きやすい豚肉食や狂犬病などを介在する犬を不浄と忌む半面、グルーミングで清潔を保ち、人と寝起きを共にする猫は清浄な動物だと考えられたのです。
初期のキリスト教では人間以外の動物は大切にしなくて良いとしたのに対し、ムハンマドは動物も神が人のために創られたものなのでむやみに虐待してはならないと説きました。
アッラーの言葉を記したクルアーンはイスラム教徒にとって最重要事項、それを聞き取った預言者ムハンマドの言葉はクルアーンに等しく重く、このムハンマドが猫好きだったことがイスラム社会における猫の地位を高くしたと言えるでしょう。
ムハンマドは猫を閉じ込めて餓死させた女性を説法で強く糾弾し、礼拝に行こうとしたら外套の袖の上で愛猫のムエザが寝ていたので袖を切り落とすなど猫愛に満ちたエピソードが伝わっています。
ちなみにその後、ムハンマドが帰宅するとムエザはまるでお礼を言うように端座してお出迎えしたので彼は9つの命を得て天国に行けるよう、また高いところから落ちても平気なように祝福を与えたそうです。飼い猫のお出迎えに嬉しくなっちゃうのは遠い昔の聖人も私たち猫飼いとして変わりませんね。
この祝福には別の説もあり、”猫の父”とその名を訳される側近のアブー・アライラの飼い猫が木陰で休んでいたムハンマドを毒蛇から救った時にムハンマドが猫の額と背を撫でて祝福したため、猫の額にはMの模様が付き、どんなに高いところから落ちても背中を打つことはなくなったとも言われています。
古代宗教における猫②インド~東南アジア
猫がエジプトから古代ペルシャに流出した頃に一旦お話を戻します。ギリシャからローマ帝国に伝わった一方で、ペルシャからインドにもたらされた猫たちはどのような位置づけに置かれたのでしょうか。
インドのヒンドゥー教では唾液を穢れとみなします。そのため、始終体を舐めている猫はイスラム教とは逆に不浄な生き物とされてしまいました。高位の神ガネーシャの乗り物とされるネズミを食べてしまったり家畜を襲う事があるのもまた、マイナスポイントだったようです。
インドでの猫の位置付けが低いものであったせいか、初期の仏教ではお釈迦様が病の床に就いたとき、薬を取りに行ったネズミを食べてしまったとされたり、すべての動物が勢揃いしたお釈迦様の入滅にネズミを捕っていて立ち会わなかった等の不名誉な扱いをされています。
ところがいざ、仏教がシルクロードを通ってその教域を広げていく段になると立場一転、仏典をネズミから守る存在として扱われ始めます。タイでは仏典の守り手として寺院で大切に飼われ、中国、日本へも仏典と共に好意的に迎えられました。
ちなみにヒンドゥー教では猫を好まないと書きましたが、ヒンドゥー教と仏教が混ざり合って独自の発展を遂げているバリヒンドゥーでは本家ヒンドゥーとは逆に猫を女神サラスヴァティの化身として大切にしています。
バリ(インドネシア)やタイのお土産に木彫りの猫は人気のアイテムですが、どちらの国もバリヒンドゥーやイスラム教徒が多く、猫に親しむ宗教的土壌があるからなんですね。
道教の国ではどうでしょうか。中国では猫の神秘的な側面が強く捉えられ、金華猫や猫鬼といったあやかしが登場しますが、宗教的に是非もないようです。同じく道教の国、お隣ベトナムでは干支の兎年が猫に代わりますが、単に発音が似ているだけということでこれもまた宗教的な背景は無いようです。
日本の宗教と猫
仏教と共に日本にやってきた猫の宗教上の立場はどんなものになったのでしょうか。仏典の守り手である以上に見た目の愛らしさから平安の貴人たちに愛され、戦国時代にも外交上の贈答品としてやりとりがあったと記録されています。
庶民に行き渡るようになってからは養蚕、農業、また漁業の守り手として信仰の対象にもなりました。ただ、養蚕業においてはリアル猫はネズミを捕まえるのと同じように蚕にも手を出すことがあったため、猫石や猫絵といった猫を模したものを祀るのが一般的だったようです。
そうした中で猫の像を祀る招き猫文化が発展し、養蚕業以外にも商売の守り神として定着していきます。
仏教と同じく私たちになじみの深い神道ですが、古事記や日本書紀といった神道の原典に猫は登場しません。神社で祀られる神様は原則的に記紀に記された神々や歴代天皇、偉人などです。稲荷社の狐や天満宮の牛は後世に仏教との習合やご祭神の逸話から派生した眷属であり神ではありません。
厳密にいえば神道に動物神はいませんが、それでも猫を祀る民間信仰としての社は全国的に散見され、猫がいかに日本人の生活に根差していたかを今に伝えています。
最近では和歌山電鉄のたま駅長の死後、大がかりな社葬が神式で執り行われました。神葬祭は故人を神にするための祭祀です。これによってたま駅長はたま大明神となられました。ここまで正式な手順を踏んで猫を神格化したのは他に例のない事です。
このニュースは世界中のメディアで取り上げられ、日本では猫が神になるのかと驚きをもって受け止められました。一神教では考えられない事ですが、多神教における神とは自然のことですので、猫が神になるのもまた自然な事と言えるでしょう。
猫はもはやそれ自体が宗教
人類を可愛さで魅了した3,500年前のエジプトからこちら、猫たちはあらゆる宗教で神でもあり悪魔でもありました。
これほどまでに立ち位置を変えてきたのは偏に猫が人類にとって身近であったということ、それ以上にひときわ特別な存在だったことを示しているに他なりません。極端に尊ばれたり忌まれたりするのは取るに足らない存在ではない、という事の証明です。
筆者は大学で神道を学びましたが、そこで神道の神とは自然、すなわち自ずから然るものであると教わりました。太陽の恵みや風、水の流れや木々の生育、人為を超えて起きる事象すべてに神を感じるという非常に原始的な宗教観です。
そこから考えてみますと、猫様がしっぽで卓上のものを薙ぎ払われるのも自然、トイレ砂を巻き散らかされるのも自然なら、気まぐれに猫パンチを繰り出されるのも自然。受け入れるよりほかに無い猫様からの試練はすべて人為を超えて自ずから然るもの…!
そう思うと陽だまりで丸くなる尊い寝姿のなんと神々しいこと。もう、猫が神様でいいんじゃないでしょうか。
Twitterではきあ(@kia_ruruten)さんが猫預言者さながらに旧約肉球書を記され、ネット界隈の猫信奉者をメロメロにしています。
今この猫記事を読んでいる猫好きなあなたも立派に猫の信徒です。さあ、今宵もちゅーるをお供えし、御名を復唱して撫で奉り、猫様の安寧がとこしえに続きますようご祈念申し上げましょう!