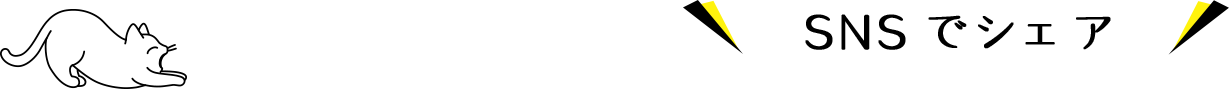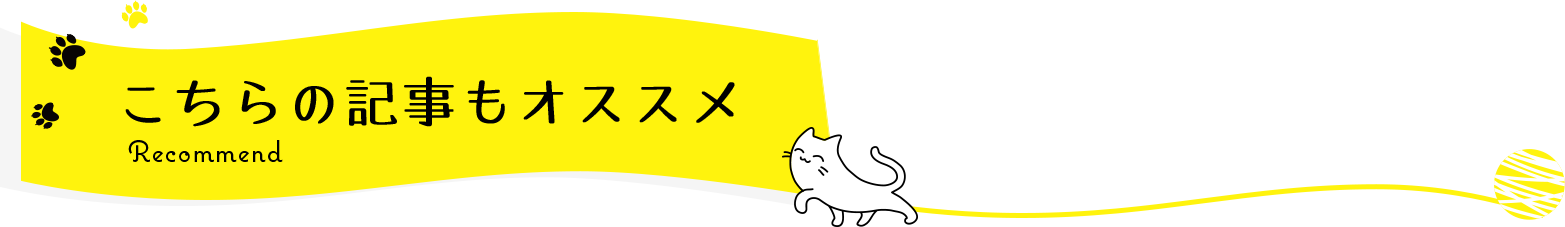猫は姿も形も申し分なく愛らしく、特にその毛並みは短くても長くても、単色でも模様付でも、いずれも変わらず見て美しく触って柔らかく私たちをうっとりとさせてくれます。
猫の飼い主さんなら、愛猫を抱き、その手触りに癒されながら「ずっとそばにいてくれたらいいのに」そう願った事があるのではないでしょうか。しかし猫の一生は私たちに比べてあまりに短く、いつかは別れなければなりません。
それでも姿だけはずっと一緒にいられるとしたら、その方法を選びますか?今回は猫を剥製にして残す方法と実際に剥製にした人たちのお話です。
新しいお別れのかたち、剥製葬
剥製といえば、ひと昔前には旅館や個人宅の床の間に置いてあることも珍しくなく、なんなら頭が付いたままの本物の狐の襟巻は人気の高級おしゃれアイテムでした。
あまり見る機会のない動物のリアルな姿をじっくりと観察できる剥製ですが、生きていたものを加工して作られるというプロセスから、残酷に感じる人も少なくないようで、昨今では博物館や資料館の展示物以外では見かける事も少なくなりました。
まずは剥製の作り方を簡単におさらいしましょう。剥製は動物の亡骸から毛皮を剥ぎ、防腐処理を施したのちに除去した内臓や骨格の代わりとなる損充材を内部に詰めることで生前の姿に近づけて保存する技術です。
かつては綿や木材などを詰めて作られていたため、生前のシルエットとは異なる仕上がりとなってしまう事もありました。昨今では合成素材の原型に毛皮を被せて作る手法が多く取られており、筋肉の盛り上がりや質感などの再現性も高く、より生前の姿に忠実な仕上がりが可能となっています。
こうした技術で愛猫を死後、剥製にして手元に留めようとするのが剥製葬です。
これまで剥製と言えば、学術標本や美術品、ハンティングトロフィーが主な目的であり用途でしたが、博物館の予算縮小や狩猟人口の減少に伴ってそういった発注が減る一方で、犬や小動物、そして猫などの家庭で飼われているペットの注文が増えていると言います。
価格は業者によって、また扱う動物によって異なりますが、猫の場合は20万円前後、子猫の場合は多少下回るところが多いようです。ポーズ付けや特別な注文の場合はそれに応じて価格も変動します。
愛猫の亡骸を冷凍・冷蔵して剥製業者に送り、完成したら送り返されるのが一般的な流れとなります。業者によっては一般のペットは扱わなかったり、釣果の魚類のみを専門に行っているところもあるため、飼い猫の剥製が可能か問い合わせておく必要があります。
打ち合わせの際に確認する点は価格、飼い主側が取るべき手順に加え、希望するポーズ、義眼の有無や色形などです。表情の仕上がりによってはまるで別猫になってしまうおそれもあるため、会社のHPなどであらかじめ仕上がりの傾向を確認しておくと良いでしょう。
剥製に似た手段としてもうひとつにはフリーズドライがあります。こちらは亡骸の内臓を抜いた後、特別な機械に入れて1、2ヶ月かけて真空乾燥を行う事で生前のままの姿を保存する技術です。例えが良くなくて恐縮ですが、いわばカップラーメンのかやくの要領で、元々は食品保存の技術でした。
毛皮以外は作りものになってしまう剥製とは違い、舌や歯なども含め体がほぼ丸ごと残りますが、筋肉や腱が用を為さなくなっているために本体だけで自立することはできません。
殆どが水分で出来ている眼球もまた、残りません。義眼をはめる事も可能ですが、生前の雰囲気を損なう可能性があるため、眠り目で、体も丸く眠っているポーズでの仕上がりが推奨されています。
エンバーミングの意識が強いアメリカでは家庭用の機械も存在するそうなのですが、日本では開発されておらず、輸入も難しいとの事で2018年現在は静岡県の駿河剥製標本社のみがこの加工を請け負っています。
剥製葬のメリットとしては「いつまでも愛猫の姿を手元に留めて置ける」この一点に尽きます。とあるペット葬儀社のブログでは剥製葬を始めたきっかけは、長年連れ添った愛猫に旅立たれた高齢の飼い主さんが「眠ったままそばに居てくれるだけでいい」という言葉だったと綴られています。
愛くるしいその姿をいつまでも留めておくことによって、ペットロスが軽減されるという考え方もあるのです。
逆にデメリットはどうでしょうか。見慣れている愛猫の顔だからこそ、微妙なバランスの違いなどの違和感を大きく感じてしまうもの。思ったような仕上がりとならず「生前の面影がなくなってしまった」という事もあるようです。
また、剥製はいわば死体です。そこにいるのに動かない。触ってももう柔らかくも暖かくもない。死んでしまった現実を目の当たりにし続ける事にもなり、ペットロスをより強く感じてしまう場合もあります。
体だけを残すことが果たして慰めとなるのか、より深い悲しみとなるのか、ご自身の心や家族とよくよく相談して決断されることをおすすめします。
実際に剥製となった猫たち
身近な存在である猫を剥製にすることは、どちらかといえばセンセーショナルに受け止められる出来事であり、表舞台に登場するたびに人々を驚かせました。猫の剥製として有名な例をいくつかご紹介しましょう。
ハンドバッグになった「トム」
2016年、ニュージーランドの剥製師クレア・サード氏が自作のハンドバッグをオークションサイトTRADEMEに出品するや瞬く間に賛否両論、物議の的となりました。
たとえばそれが兎のリアルファーを使ったバッグであればありふれたアイテムであり、ここまで話題になることは無かったでしょう。しかしこのバッグは本物の猫の毛皮で作られており、ご丁寧に剥製化した頭部までついていたのです。
トムと名付けられたこの猫バッグは当初日本円にして10万円ほどで出品されましたが、批判を受けて70円に値下げ、入札バトルの末、最終的に4万円ほどで落札されました。
猫はサード氏が見つけた時には既に交通事故で死んでおり、頭部以外は損壊していたそうです。同氏は亡骸を3ヶ月冷凍庫で保管、飼い主が見つからなかったこともあり、バッグに加工しましたが、それからも7年間手元で保管していました。
彼はトムを殺したわけではなく、今までに剥製にするために動物を手にかけたことは無いとコメントしていますが「猫の亡骸で商売をしようとした」「猫の亡骸を冒涜した」として批判にさらされてしまいました。
剥製師という職業柄、亡骸に対する考え方が我々一般の飼い主とは少し違うのも道理かとは思います。バッグ自体の出来栄えは非常に精巧で、生前の猫の雰囲気を損なうようなものではなく、好意的なコメントも皆無ではありませんでした。
実際トムは端正な顔立ちの美猫であり、顔の部分だけ見る限りは可愛くすらありますが、バッグから生えているとやっぱりちょっとびっくりしてしまいますね。
ラジコンヘリになった「オーヴィル」
交通事故に遭って死んでしまった愛猫を剥製にしてプロペラ付きのラジコンヘリにしてしまったのはオランダのアーティスト、バート・ヤンセン氏です。
飛行機の生みの親ライト兄弟の弟のほうの名前に因んでオーヴィルと名付けられたその猫は名前の通り、空を眺めるのが好きでよく鳥たちを見上げていたそうです。
オーヴィルの死後、ヤンセン氏は愛猫の大空への憧れを叶えてあげたいと剥製化したのちにラジコンヘリの専門家に依頼、ムササビのように四肢を広げて空を飛ぶオーヴィルコプターとして甦らせました。
2012年にアムステルダムで行われたアートイベントに出展された際には、実際に飛行する様子も披露されました。その後もオーヴィルの誕生日には更なる改良がくわえられ、より安定的に飛行できるようにカスタムアップされたとの事です。
同氏は批判を避けるためか「これはあなたの履いている靴と同じ、既に死んでいるなめし皮です」とコメントしていますが、ネット上ではやはり驚きと困惑のリアクションが多く見受けられます。
オーヴィルコプターを見つめるヤンセン氏の眼差しからは悲しみや慈しみを感じられるような気もしますし、これもひとつの愛情の示し方なのかもしれません。
子猫の剥製師ウォルター・ポッター
19世紀、ビクトリア朝時代のイギリスでは貴族たるもの紳士たるもの、自宅に「ヴンダーカンマー(驚異の部屋)」と呼ばれる私設博物室を設けて珍しいものや価値のあるものを蒐集するのが嗜みでした。
そんな時代を背景に活躍したのが剥製師ウォルター・ポッターです。擬人化ポーズを取らせた小動物の剥製を教室や食卓といった舞台装置の中にジオラマ風に展示する作風で82年の生涯のうちに1万体を超える剥製を製作しました。
彼の死後、オークションにかけられて散逸してしまった作品を集めた展覧会が2016年、ニューヨークのモービッド・アナトミー・ミュージアム(病理解剖学博物館)で開催されました。
特に来場者の目を惹いたのが「子猫の結婚式」と呼ばれる作品で、19体の子猫の剥製が盛装して司祭や新郎新婦、参列者を演じています。
死んだ子猫、という事実を意識から外して鑑賞する限りは非常に可愛らしく、表情付けや世界観まで実に丁寧に作られています。当時はこうした剥製もごく一般的なインテリアとして位置づけられ、家庭にも飾られていましたが、現代ではグロテスクに感じる人も少なくないようです。
同ミュージアムには他にも擬人化された剥製作品が多数収蔵されていましたが、資金不足のため2016年末に閉館しています。ウォルター・ポッターの作品は写真集も発売されていますので、興味のある方はお手に取ってみて下さい。
特にヨーロッパでは伝統的に娯楽や嗜みとしての狩猟の後に獲物を剥製化したり、また人間も死後、遺体をそのまま埋葬する宗教観の為か、日本ほど剥製に抵抗が無いようで、現代でも剥製葬を行う飼い主が少なくないようです。
海外の例が続きましたが、実は日本にも有名な猫の剥製があります。
谷崎潤一郎書斎の「ペル」
耽美派の作家、谷崎潤一郎は著作の中で「動物の中で一番の縹緻(きりょう)好しは猫族類でせうね」と語るほど大の愛猫家で、その作品にも猫を思わせる女性像や猫に振り回される男女が多く登場します。
特にペルシャ猫を愛し、多い時には10頭を超える猫を飼っていましたが、とりわけお気に入りだったのは伊豆の静養時代に飼っていたペルという名の猫でした。猫好きとはいえ書斎には決して猫を入らせなかった谷崎氏ですが、ペルだけは唯一出入りを許されていたそうです。
それほどにお気に入りだったペルは死後、剥製となって彼の執筆を見守り続けました。時に昭和20~30年代、今よりも剥製の置物に寛容な時代ではあったと思いますが、飼い猫を剥製化するというのは前衛的な事であったと見えて出版社が大騒ぎになったようです。
ペルは現在も兵庫県芦屋市にある谷崎潤一郎記念館に収蔵されており、常設展示はされていませんが、特別展の時などに見る事ができます。
猫の剥製に抵抗を覚えるのはなぜでしょうか?
ところで今更ですが、剥製はお好きでしょうか。私はかなり好きな方です。大型猫の剥製が一堂に会する静岡県伊東市の猫の博物館、大型哺乳類の剥製の群れが圧巻な国立科学博物館、いずれも剥製見たさに赴くほど剥製に魅力を感じています。
それでも愛猫が死んだとき、剥製にしたいとは思いませんでした。「剥製は肯定するけれど愛猫を剥製にはしたくない」この矛盾する心理について掘り下げて考えてみます。
愛猫は長患いの末の最期でしたが幸いにして安らかな死に顔をしており、家族と「死んでいてもうちのこ可愛い」「このままずっと置いておきたい」と言い交わしては泣いておりました。飼い主目線では世界一美しい猫でしたので、このまま土に還すのは非常に惜しいとも感じていました。
しかし、この猫の亡骸が切り開かれる事になるのが単純に嫌でした。そして、もう動かない愛猫を眺めて暮らすのは埋めてしまう事より嫌でした。それは馴染みのない個体の剥製を心穏やかに鑑賞するのとはまったく違う感覚だったのです。
既に死んでいるものを剥製にすること自体は別段かわいそうとは思いません。オーヴィルコプターの作者が語るように「履いている靴のなめし皮」と死んだ猫との間に物質的には違いは無い筈なのです。
普段使いのものの素材として天然皮革は一般的ですし、コートにリアルファーがあしらってあっても別段残酷に感じない人が殆どのはずです。
しかし、猫のこととなると話は別で、それが既に死んでいた猫であっても亡骸に手を加える事に抵抗を覚える人が(私も含めて)少なくないのはなぜでしょうか。
思うに、例えば愛する配偶者が亡くなったとしてもその遺体を剥製にして遺しておきたいとは思わない、という事なのでしょう。猫を単なる愛玩動物ではなく、より身近な同格のパートナーと捉えている人が多いという事のあらわれではないでしょうか。
とはいえ、剥製葬を否定はしません。ヘリコプターになったオーヴィルや谷崎潤一郎のペルは決して愛猫の亡骸を冒涜するものではないと思いますし、剥製になって動かなくとも「ただもうそばに居てくれたらそれでいい」という気持ちには強く共感を覚えます。
ペットロスの感じ方や乗り越え方は飼い主の数だけ存在しています。猫だって飼い主を悲しませたくて死ぬわけではありません。姿だけでも残って慰めとなるのであれば、猫も本望ではと考える事もできます。
猫の剥製、それも亡き愛猫を偲ぶ方法の一つです。